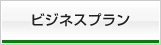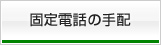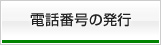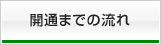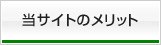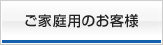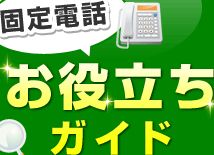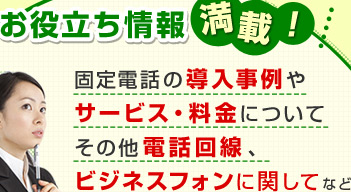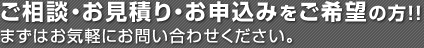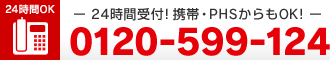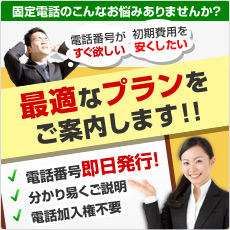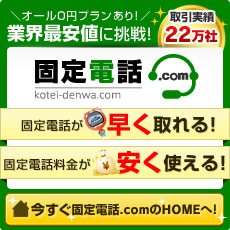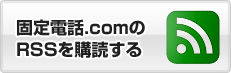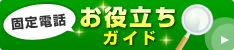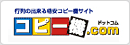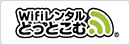メタル回線と光ファイバーはどう違うの?

-

-


0120-962-057
電話回線をどう選べばいいか分からないという方はいませんか?
これから新規オフィス立ち上げや、移転などに際して、新しく電話環境を構築しなければならないというときには、ぜひ知っておいてほしいことがあります。
それは、メタル回線と光ファイバーの違いです。
それぞれにはメリットとデメリットがあり、使用状況によってふさわしいものが決まってきます。
そこで、今回はメタル回線と光ファイバー回線の違いをご紹介します。
メタル回線とは?
メタル回線の電話回線といえば、アナログ回線とデジタル回線です。
これらの二つの回線は、銅線に音声データが乗って伝えられていきます。
このメタル線を使った高速データ通信の技術のことをDSLと呼びます。
いわゆる「ADSL」も、このメタル線を利用した回線となります。
従来のアナログ回線の電話を利用していた人にとっては、非常に都合が良くなっています。
なぜなら、同じメタル線のままで、電話回線もインターネットのデータ通信も行えるからです。
伝送されるデータの周波数は、音声通信とは異なるため、同時にメタル線が使用できるのです。
これがメタル線の大きなメリットといえるでしょう。
一方、メタル線は、電話局からの距離が遠ければ遠いほど、伝送の減衰が大きくなってしまい、速度が落ちるというデメリットもあります。
他の電波が交じったり、音声がかすれたりといった音声品質の面でどうしても劣ってしまうのです。
光ファイバーとは?
一方、光ファイバーの電話回線といえば、光電話です。
光ファイバーは、従来のメタル回線と比較して、長距離でも高速に通信が行えるところに特徴があります。
電話局からの距離にまったく影響がないのです。
また、光の点滅によって信号を伝送するので、電気信号と比べて厳しい環境下でもノイズの影響が少ないというメリットもあります。
一方、傷や曲がり、汚れに弱いというデメリットもあり、突然のシステムダウンも起き得るといわれています。
また、利用者からすれば、停電時に使えないというのは残念なところです。
これらのメリット・デメリットをよく考えて、電話回線を選びたいところです。
ビジネスの現場で活躍するビジネスフォン(2)

ビジネスフォンと家庭用電話機は、どんな違いがあるのでしょうか。基本的には家庭で使われる電話機が家庭用電話機で、職場のオフィスなどビジネスの現場で使われるのがビジネスフォンです。その機能面での違いについてご紹介していきます。
家庭用電話機の特徴は?
家庭用電話機とは、局線が1外線(割り振られる番号が1つ)で使用するタイプの通信機器のことです。電話機が何台あったとしても外線が1チャンネルしか対応していないため、電話またはFAXを1台使用していれば他から発着信できません。あくまで1台ごとの利用に限定されるのが特徴です。なお、この家庭用電話機は一般的に家電量販店で販売されており、留守番電話機能対応の親機1台と、コードレス子機複数台の組み合わせが主流です。家庭用FAXにコードレス子機が付いているタイプも同じと言ってもいいでしょうね。
この家庭用電話機をオフィスで使用すると、他部署へ連絡する際、内線で回すことができず、外線を使用するため同じ社内なのに通話料金が発生してしまうといったことが起こります。また、電話を受けた人以外への電話だった時、その人はわざわざ電話機が設置されている場所まで行かないと電話にでることができないという、現実的にはあり得ないシチュエーションが生まれてしまいます。
ビジネスフォンでは何ができる?
一方、ビジネスフォンとは複数の外線と内線を共有して制御できる電話機のことになります。複数の外線と内線を制御する主装置と、複数の端末機(専用電話機)から構成されており、容量の大きいものになると数百台の子機も制御できるのです。つまり、ビジネスフォンとは電話機単体のことを指すのではなく、主装置と専用電話機の組み合わせによる電話装置システム全体を指しているのです。
ビジネスフォン導入のメリットは、少ない電話回線・番号を多くの電話機で共有できることです。例えば、もし家庭用電話機をオフィスで利用するなら、社員の数だけ電話機を設置しなければならないのはもちろんのこと、その台数ぶんの電話回線が必要になります。電話回線の回線数ぶんだけ電話番号も異なり、同じ電話番号を社員全員で使うことはできません。一方、ビジネスフォンなら複数の回線を1つの主装置に収容でき、接続された電話機へ振り分けることが可能となります。例えば電話回線数自体は1回線でも、外線着信は2台以上の電話機で受けることができるのです。ビジネスフォンを導入することによって、必要最小限の回線をそれより多い数の内線電話で共有できるため、利用方法は変わらないまま、導入費用や月々の基本使用料が大幅に削減できるメリットがあります。
ビジネスの現場で活躍するビジネスフォン(1)

オフィスなどに設置される電話機は「ビジネスフォン」と呼ばれる、一般家庭で使われる電話とは少し違った電話機になります。ここでは、数回にわたってビジネスフォンについての基本的な情報をご紹介します。
ビジネスフォンにはどんな歴史があるの?
ビジネスフォンの大きな特徴として、内線と外線があるということを覚えておきましょう。その上で、国内におけるビジネスフォンの歴史としては古く、1868年にスコットランド出身の商人であるトーマス・グラバーが、長崎にあるグラバー邸から高島の小島にある自らの別荘に海底ケーブルを引き、日本初の私設電話を設置したことが始まりです。その後、1902年ごろから各企業に私設電話の設置が広がり始め、外線電話である加入電話と内線電話の私設電話との接続が可能になりました。ちなみに、このころの内線の交換は交換手による手動での交換でした。1940年代にはステップバイステップ交換機が導入され、内線相互の自動交換が可能となりましたが、外線との接続はやはり交換手によって行なわれていました。
大きな変化が訪れたのは1960年代になってからです。事業所集団電話よりダイヤルインサービスが始まり、外線から内線への直接着信が可能になりました。これが現在のビジネスフォンの誕生と言えるでしょうね。これ以後、ビジネスフォンは急速な進化を遂げていくことになります。
基本的には内線と外線を使い分ける機能から
ビジネスフォンを簡単に説明するなら、複数の外線と内線を共有できる電話機のことを指すと言っていいでしょう。外線とは、正確には外線電話のことを指し、公衆回線を使って着信するもの、つまり通常の電話のことです。一方、内線とは専用線や構内交換機、主装置を使用して公衆電話網を使わずに通話できる電話のことです。私設電話とも呼ばれており、電話料金がかからない利点があります。当初は会社など同じ組織内での通信で使用されていましたが、内線を管理している主装置に公衆回線も接続し、外との通話機能も持たせるようになりました。ビジネスフォンとは、一般的に主装置に公衆回線も接続された内線電話のことをいうこともあります。
当然のことながら、こういった内線と外線を使い分ける機能は家庭用の一般的な固定電話機には備わっていません。比較的規模の大きな企業では、フロアの異なる部署にいる社員との連絡や、外線で着信した通話を内線機能を使って担当者へ取り次ぐといった機能が必要となります。こういった需要に応えるように、ビジネスフォンの機能が進化してきたと言ってもいいでしょう。
マイライン選びの裏ワザをご紹介

電話回線の会社を選べるマイライン。アナログの固定電話を利用するなら、使わないと損をするサービスですね。でも、普通にマイラインを選んでしまうとお得にならないこともありますよ。そこで、マイライン選びの裏ワザをコッソリと教えます。
マイラインは後から変更することもできる
電話関係の仕事をしている知り合いの人から、マイラインの登録を強く勧められ、やむなくマイライン登録をしてしまったという声をよく耳にしますね。利用する電話会社を自分で選んで、お得になるはずのマイラインなのに、付き合いで入らなければならないというケースがあるのはおかしな話です。しかし、実はマイラインは一度登録しても変更できるんですよ。
変更には800円の手数料が必要になりますが、とりあえず付き合いで登録しておいて、あとで変更すれば相手の方の顔をつぶすようなこともなくスマートにマイラインを登録できるのでます。また何らかの事情で、絶対に登録し続けなければいけない場合もあるかもしれません。この場合はマイラインの恩恵を受けることができないかもしれません。
そういったケースの場合は、その電話会社をどう使ったら得になるかを自分の利用状況と合わせて各社ホームページで調べましょう。もし、それでも他社のほうが割安な場合は、通話ごとに番号の頭に「122」と「電話会社の識別番号」をつけて通話する方法で利用すれば、損をすることはありませんよ。
他の電話会社を簡単に使うテクニック
マイライン登録をしても、通話ごとに「122」+「電話会社の4桁の識別番号」をつければ、他の電話会社が利用できますが、実際問題わざわざ通話のたびに、このような手間を掛けるのは面倒ですよね。でも、最近の電話機にはだいたいワンタッチダイヤルや短縮ダイヤル機能が搭載されています。電話機の特定のボタンに電話番号を登録すると、そのボタンを押すだけで登録された電話番号にダイヤルされるという機能です。電話機によってはボタンではなく番号で登録するケースもあります。そこに「122」+「電話会社の4桁の識別番号」を登録してしまえばいいのです。ワンタッチダイヤルがある電話機なら、そこへ登録しておけば非常に便利です。
そもそも論ではあるのですが、マイラインの登録を変更する場合に申込者が800円の手数料を負担しなければならないのが理不尽だという声があります。そして、よっぽど通話料金が安くなり、しかも定期的にその番号と通話するということでもない限り、800円の手数料を支払ってまで他社サービスへ乗り換えようという人は実際あまりいないのが現状です。そして、光ファイバー回線を利用した電話やIP電話が伸長してきているため、こういったマイラインのサービスもいずれは廃れていくのかもしれませんね。
ひかり電話にするなら「光コラボレーションモデル(光コラボ)」を活用しよう!
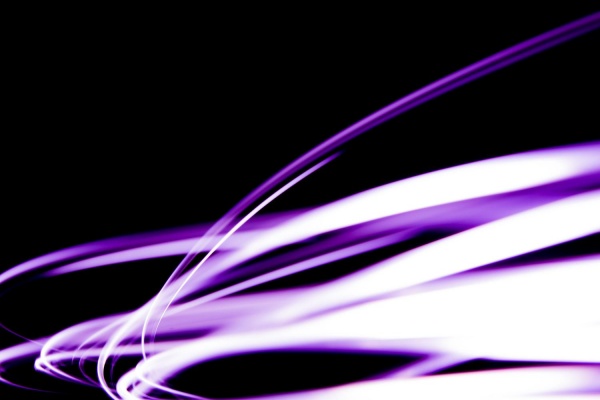
電話やインターネットも光ファイバー回線の時代です。しかも昨年から、NTT東日本/西日本がフレッツ光で使用しているインフラを、希望する企業へ卸販売するようになりました。これが「光コラボレーションモデル(光コラボ)」です。いろいろなメリットがありますから、これを活用しない手はありません。
そもそも光コラボってどういうこと?
NTT東日本/西日本のフレッツ光の卸サービス「光コラボレーション回線」が昨年、満を持してスタートしました。ドコモ光やソフトバンク光がいち早くスタートし、その後OCN光やビッグローブ光なども参戦し、ユーザーは幅広く比較できるようになり、お得になるチャンスが増えましたね。しかし、選択肢が増えたぶん、たくさん情報を仕入れておかないとメリットは半減し、フレッツ光の時とあまり変わらない利用料金となってしまう可能性があるのです。それぞれの光コラボの料金やキャンペーンなどを比較し、一番メリットのある光回線を選びたいものです。
光コラボとは、何なのでしょうか。簡単に言うと、今まで独占的にNTT東日本/西日本が自社で敷設していった光ファイバー回線を、希望する事業者へ卸すことで、同じ回線を提供する光コラボ事業者と契約するサービスのことです。つまり、当然ですが回線の品質自体は今までのNTT東日本/西日本の光ファイバー回線と同じなのです。
お得な光コラボ事業者を選ぶべし
光コラボ事業者は、現在のところ携帯電話事業者(NTTドコモやソフトバンクなど)、インターネットサービスプロバイダー(OCNやビッグローブなど)、全国各地の地域ケーブルテレビ会社が中心です。「コラボ」という名称でお分かりのとおり、要するに各事業者が本業として提供してきたサービスに、光ファイバー回線によるインターネット接続を組み合わせて、お得にできますよというコラボレーションが売りなわけですね。
では、どこを選ぶのがお得なのでしょうか。これは、ユーザーそれぞれによって異なってきます。例えば、スマホを現在使っていて、固定のインターネット接続を光ファイバー回線に変えたいということであれば、そのスマホの携帯キャリアの光コラボをまず検討したほうが良いでしょう。また、現在ケーブルテレビで番組を視聴しているということであれば、そのケーブルテレビ会社が光コラボを提供しているかどうか調べてみるのが一番です。つまり、現在のライフスタイルの中で、光ファイバー回線によるインターネット接続へ移行する時に光コラボを活用するというのが自然な流れだと言えます。
- 前の5件
- 次の5件